今年は自分の人生を楽しめるように「趣味を見つけたい」と、人生を豊かにしてくれそうなことにチャレンジしていくことにしました。
そこで、色んな「面白そう」「楽しそう」なことを1〜2ヶ月本気で学んで、好きになれるのか!?を試していくことにしました。
今月新しく加えたのは「芸術を楽しむ〜歴史を知ろう〜」です。
今週は平塚市美術館で開催されている「リアル(写実)のゆくえ 現代の作家たち 生きること、写すこと」に行ってきました。その時のことを紹介させていただきます。
4週目:平塚市美術館「リアル(写実)のゆくえ 現代の作家たち 生きること、写すこと」
今週は「リアル(写実)のゆくえ 現代の作家たち 生きること、写すこと」平塚市美術館まで行ってきました。(神奈川県・平塚市)
今回は、見どころは日本で最初の西洋画家といわれている高橋由一氏の作品が三点もある事です。
「平塚市美術館」今回の見どころ
今回、平塚市美術館で行われている「リアル(写実)のゆくえ 現代の作家たち 生きること、写すこと」を見てきました。
明治以降に活躍した日本の画家・彫刻家や現在活躍されている画家・彫刻家の作品を見ることができます。
今回の一番の見どころは、日本で最初の洋画家問われている高橋由一氏の作品があることです。
美術の教科書などでも見たことのある「豆腐」が金刀比羅宮蔵から平塚市美術館に来たということで見に行ってきました。
中学生の頃は、「豆腐」という絵は、ただ「「豆腐・焼き豆腐・油揚げ」が書かれていて何が凄いのかがわかりませんでした。
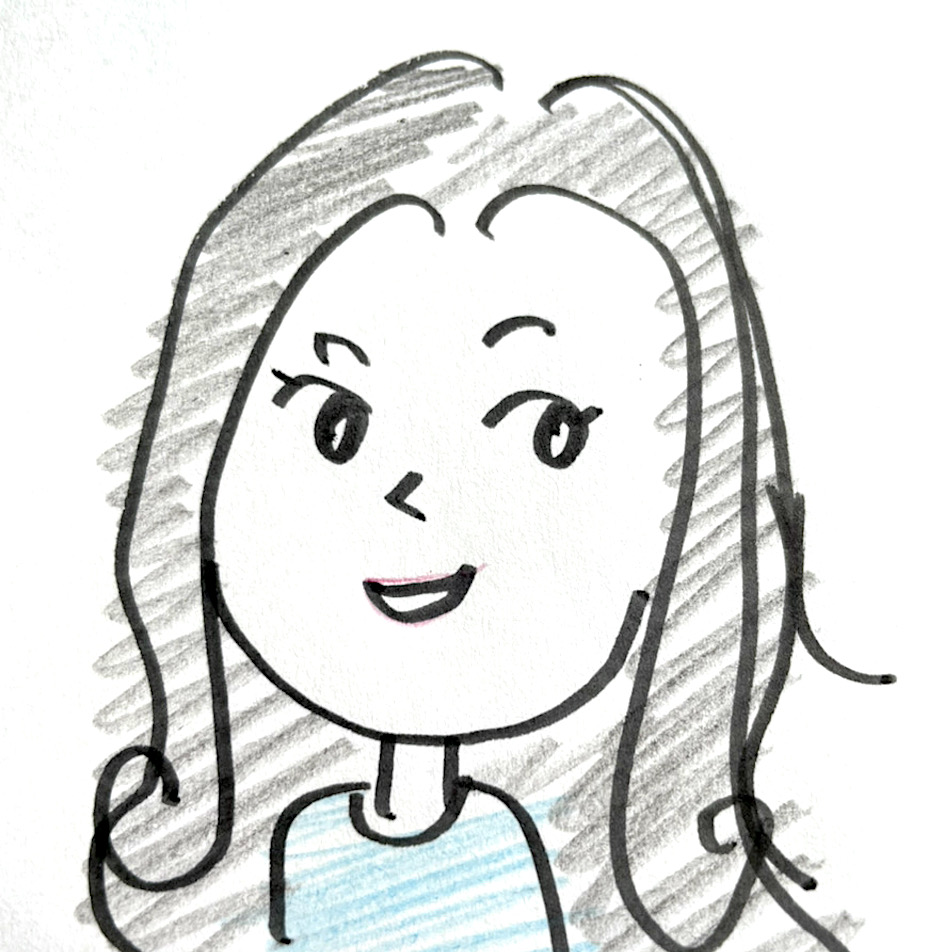
でも、日本の西洋美術は西洋とは異なった視点から見ることができて、そこのポイントをすることができるととても楽しいですよ
日本最初の正洋画家「高橋由一」氏とは?
高橋由一氏は、江戸時代に長崎の出島などから西洋絵画を取り寄せて油絵を学んでいる人はいましたが、本格的に油絵を習って描き始めた人といわれています。
高橋由一氏は、元々侍で(佐野藩(佐倉堀田藩の支藩)。ただし江戸の屋敷で勤務していた)、剣術指南の家系に生まれました。(wikipediaより)
しかし、幼少の頃から絵の才能があり、藩に出入りしていた狩野派の絵師に学びます。その後、西洋画を見て、日本の絵と違いリアルに書かれていることに衝撃を受けて、西洋画を学ぶことになります。
1862年、蕃書調所(西洋のことを学ぶ機関)に入局し、当時横浜に住んでいたイギリス人ワーグマンに絵を学びます。
日本橋浜町に画塾である天絵社を創設し、その運営資金を得るために金刀比羅宮で開かれた第2回琴平山博覧会で、天絵舎に資金援助してもらうため、作品を奉納しました。
その後は山形県の三島の行った数々の土木工事の記録画を書く仕事をしています(明治14年)。
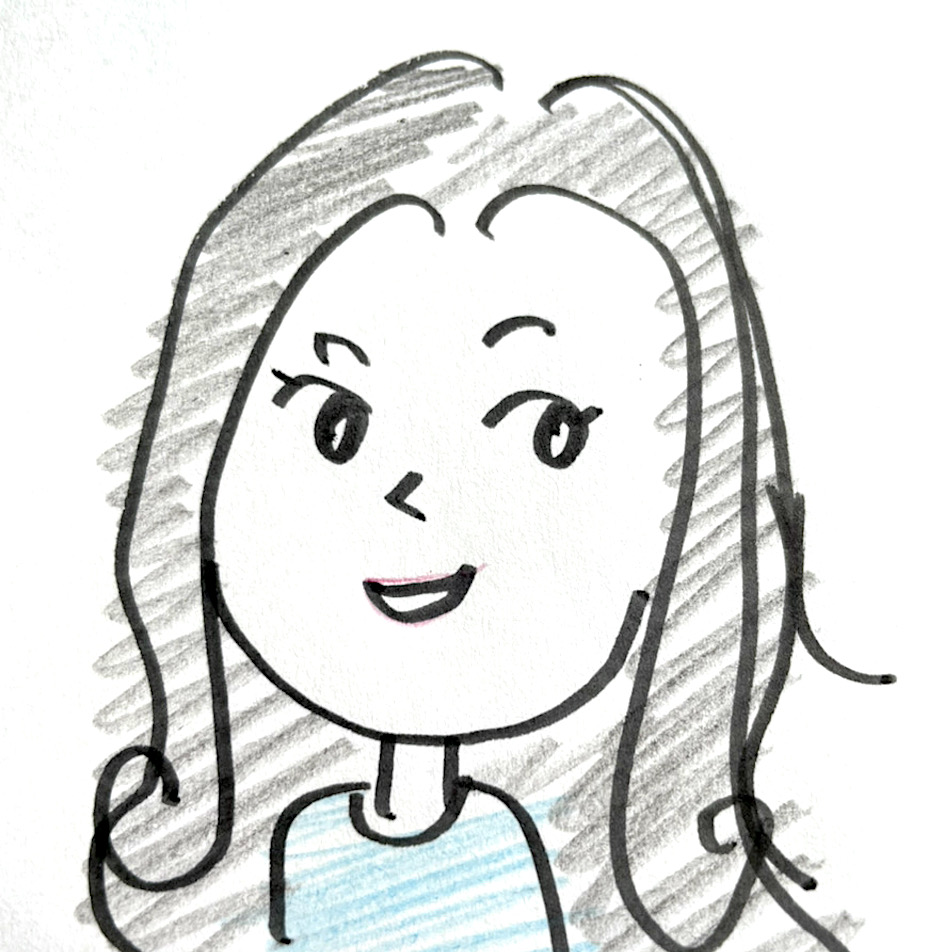
画家が記録の仕事をしているのはちょっと不思議ですね
四国の金比羅山に「高橋由一展」があり、27点の作品を見ることができます。その中から
・豆腐
・なまり
が今回平塚市美術館で見ることができるんですね。
西洋画がなぜ必要になったのか!?
日本が近代化をするために、
・記録
が必要だったためと言われています。
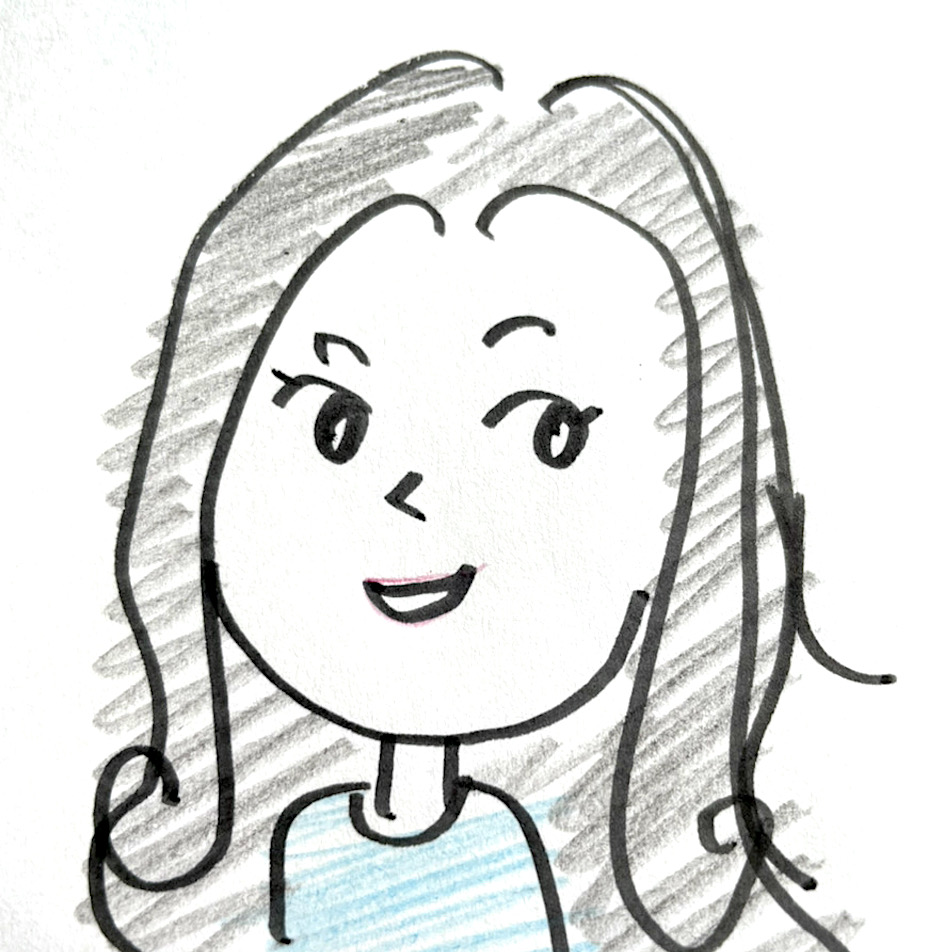
当時の写真は、撮るのも現像するのも時間がかかりますし、カラー出ないので分からないということがあったんですね
そのため、蕃書調所(西洋のことを学ぶ機関)では、語学・天文学・数学・工学・経済学などを学ぶところに、画学がありました。
日本画家はどちらかというとフリーハンドで書かれていますが、洋画は遠近法・幾何学模様などが正確性が求められることが多いです。
日本が近代化するために、物事をリアルに伝える方法を学ぶ必要があったということです。
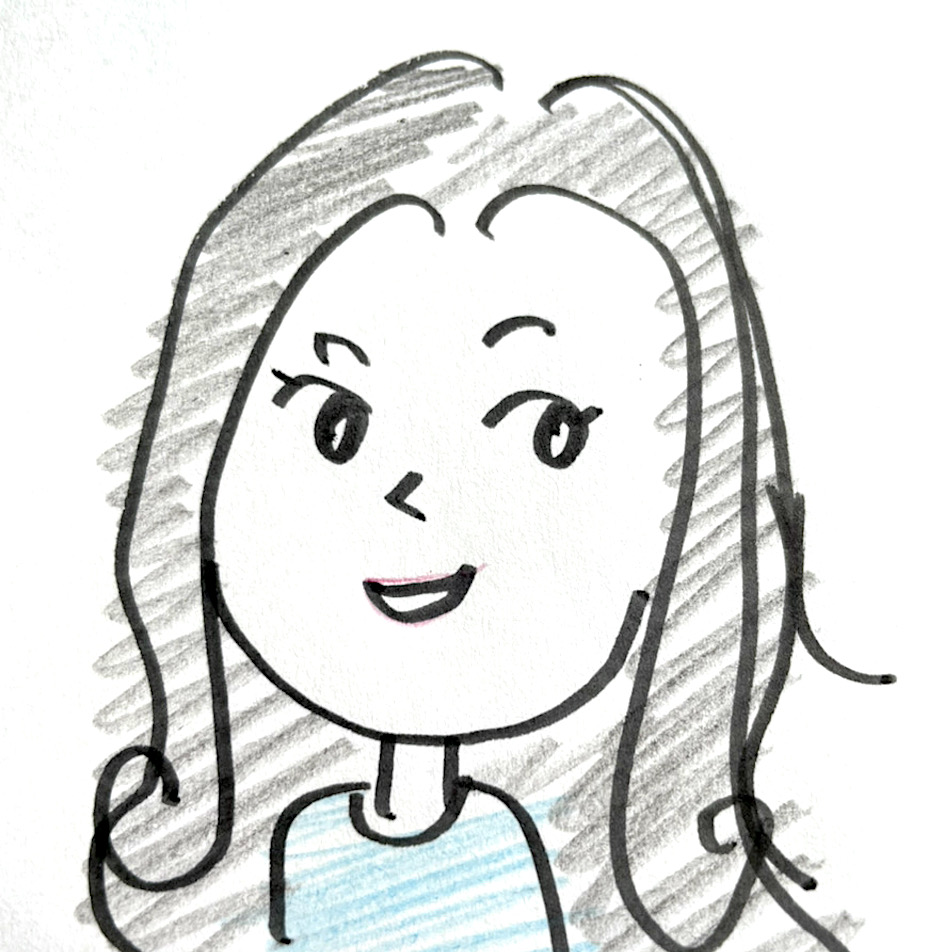
アートとして始まったわけ絵ではなく、物をリアルに伝えるために西洋画を学ぶ必要があったんですね
今まで日本画家にしか触れたことのない日本人に西洋画とは「いかにリアルな質感まで書けるのか」を知ってもらうために、みんなが知っている題材を書いて知ってもらう必要があったということです。
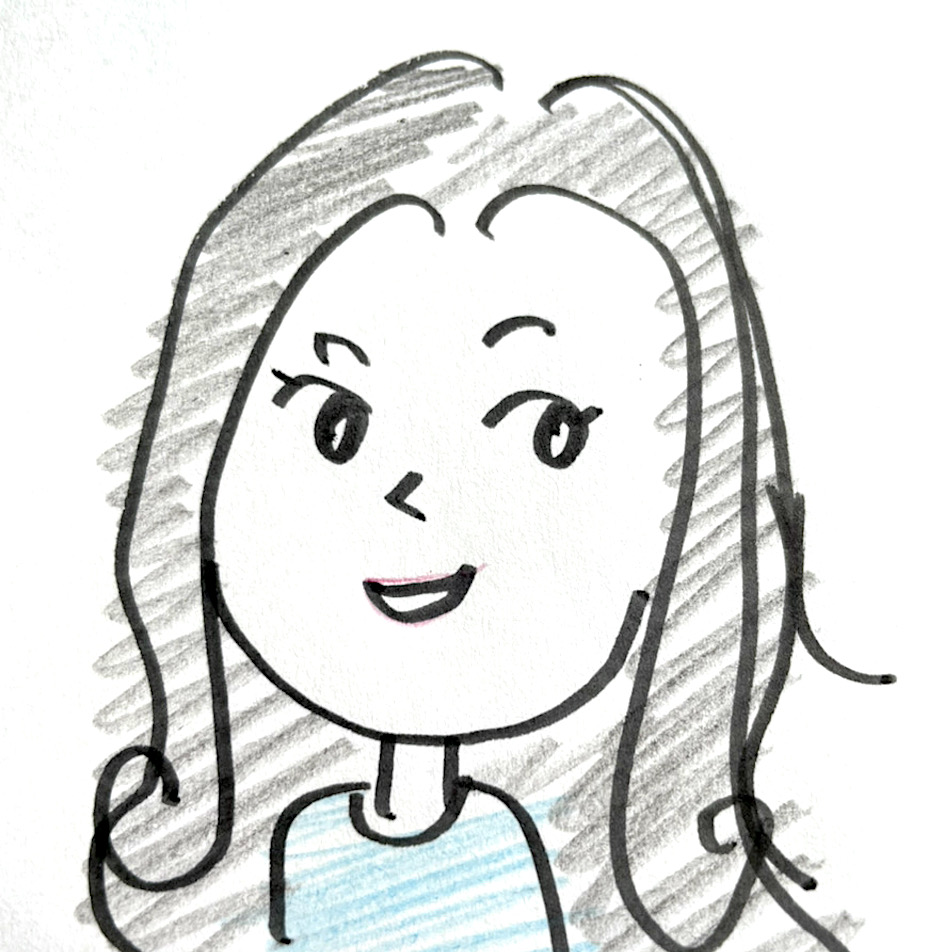
だから高橋由一氏は「豆腐」を書いたんですね。西洋の人が書いている絵画(西洋画)の目的とは違う発展を日本の西洋画はスタートとしていたとも言えます
最後に・・・
今回は「リアル(写実)のゆくえ 現代の作家たち 生きること、写すこと」を紹介させていただきました。
日本の西洋画の歴史を知ることができ、「なぜ豆腐を書いたのか?そして、それがなぜ教科書に載るほどなのか??」を知ることができました。
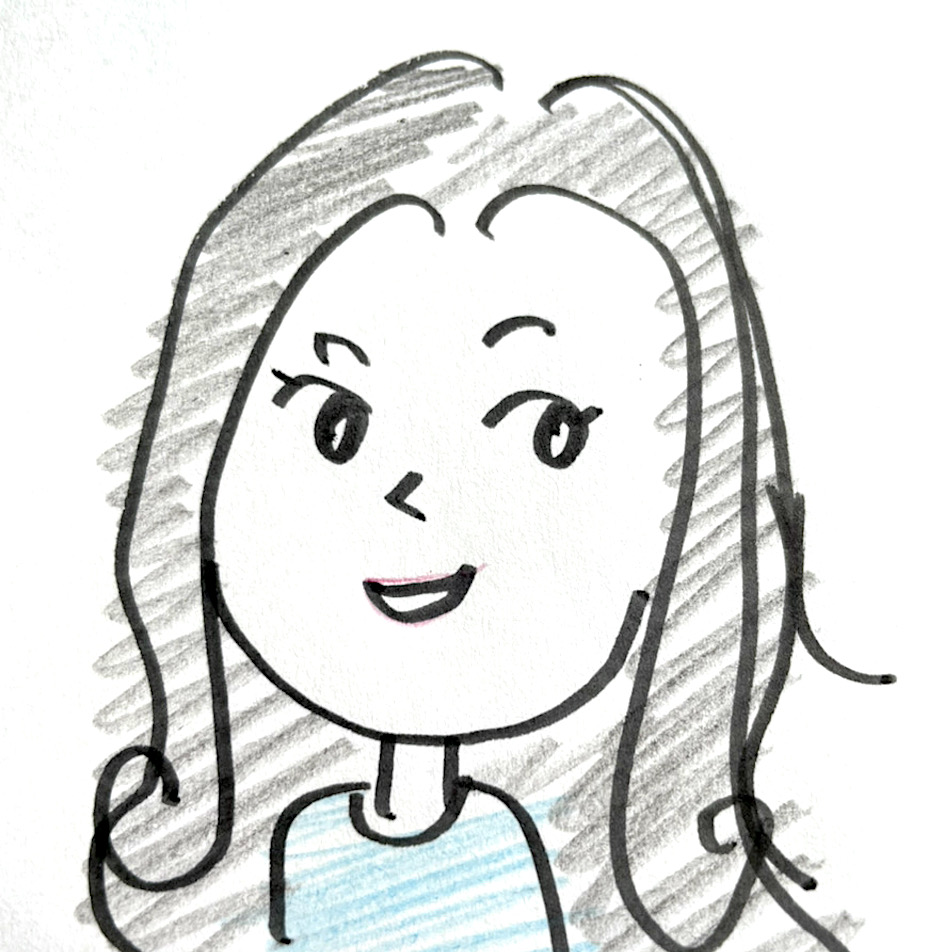
時代背景や、その歴史を知ることができると絵の見方が変わったり、親近感が湧いてきますよね
最後まで読んでくださりありがとうございました^^



コメント